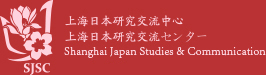(昭和四十三年七月二十日総理府令第四十六号)
最終改正:平成二六年二月二八日原子力規制委員会規則第一号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令中核原料物質の使用の規制に関する規定に基づき、及びこれらの規定を実施するため、核原料物質の使用に関する規則を次のように定める。
(定義)
第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 放射線 原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号 に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
二 管理区域 核原料物質の使用に係る施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
三 周辺監視区域 管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
四 放射線業務従事者 核原料物質の使用又はこれに付随する廃棄、運搬若しくは貯蔵の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。
五 放射性廃棄物 核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物であつて、廃棄しようとするものをいう。
(技術上の基準)
第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第五十七条の八第四項 に規定する技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、核原料物質を使用する者で原子力規制委員会の定めるものについては、第六号から第十号までの規定は、適用しない。
一 核原料物質の使用は、核原料物質の使用施設において行うこと。
二 核原料物質の使用施設の目につきやすい場所に、使用上の注意事項を掲示すること。
三 管理区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。
イ 壁、さく等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線業務従事者以外の者が当該区域に立ち入る場合は、放射線業務従事者の指示に従わせること。
ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
四 周辺監視区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。
イ 人の居住を禁止すること。
ロ 境界にさく又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立ち入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。
五 放射線業務従事者の線量等については、次の措置を講ずること。
イ 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
ロ 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が文部科学大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
六 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における放射性物質による汚染の状況の測定は、これらを知るため最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
七 放射線業務従事者の線量当量の測定は、次に定めるところにより行うこと。
イ 外部放射線に被ばくすることによる線量当量の測定は、これを知るために最も適した人体部位について、放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあつては、計算によつてこの値を算出することとする。
ロ イの測定は、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。
ハ 人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすることによる線量当量の測定は、原子力規制委員会の定めるところにより、放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場合に行うこと。
八 放射性物質による人体及び人体に着用している物の表面の汚染の状況の測定は、放射性物質によつて汚染されるおそれのある人体部位の表面及び人体に着用している物の表面であつて放射性物質によつて汚染されるおそれのある部分について、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこの値を算出することができる。
九 前号の測定は、放射性物質を経口摂取するおそれのある場所において、当該場所から人が退出するときに行うこと。
十 換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。
十一 核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄は、次に定めるところにより行うこと。
イ 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
ロ 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
ハ 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
(1) 排気施設によつて排出すること。
(2) 放射線障害防止の効果を持つた廃気槽に保管廃棄すること。
ニ ハ(1)の方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
ホ ハ(2)の方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
ヘ 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
(1) 排水施設によつて排出すること。
(2) 放射線障害防止の効果を持つた廃液槽に保管廃棄すること。
(3) 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
(4) 放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
(5) 放射線障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。
ト ヘ(1)の方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
チ ヘ(2)の方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
リ ヘ(3)の方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
(2) き裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
(3) 容器のふたが容易に外れないものであること。
ヌ ヘ(3)の方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
ル ヘ(3)の方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
(1) 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器にき裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。
(2) 当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を採ること。
(3) 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して次条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
(4) 当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
ヲ 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
(1) 放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
(2) 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
(3) (2)の方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ワ リ、ヌ及びル(ル(1)を除く。)の規定は、ヲ(2)の方法による廃棄について準用する。
カ ル(2)及び(4)の規定は、ヲ(3)の方法による廃棄について準用する。
十一の二 核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所の外において行われる放射性廃棄物の廃棄は、次に定めるところにより行うこと。
イ 放射性廃棄物は、核原料物質の使用に係る施設である放射線障害防止の効果を持つた廃棄施設に廃棄すること。
ロ イの規定により放射性廃棄物を廃棄する場合には、当該廃棄施設を設置した核原料物質を使用する者に、当該放射性廃棄物に関する記録の写しを交付すること。
ハ 廃棄に従事する者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
十二 核原料物質の運搬は、次に定めるところにより行うこと。
イ 核原料物質を運搬する場合は、これを容器に収納すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 通常の運搬状態において、核原料物質が容易に飛散し又は漏えいしないように措置され、かつ、核原料物質の使用施設の内部において運搬する場合
(2) 通常の運搬状態において、核原料物質が容易に飛散し又は漏えいしないように措置され、かつ、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 (昭和五十三年総理府令第五十七号。以下「外運搬規則」という。)第一条第七号 に規定する専用積載(以下「専用積載」という。)として運搬する場合
ロ 容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、核原料物質の使用施設の内部において運搬する場合は、この限りでない。
(1) 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。
(2) 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
(3) 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生じるおそれがないこと。
(4) 表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること。
(5) 材料相互の間及び材料と収納される核原料物質との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと。
(6) 弁が誤つて操作されないような措置が講じられていること。
ハ 液体状の核原料物質を容器(容器が外運搬規則第一条第四号 に規定するコンテナ、同条第五号 に規定するタンク(以下「タンク」という。)又は同条第六号 に規定する金属製中型容器(以下「金属製中型容器」という。)の場合を除く。)に収納し、専用積載としないで運搬する場合は、容器は、ロに掲げる基準のほか、外運搬規則第九条第一項第二号 に定める基準に適合すること。ただし、核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所において運搬する場合は、この限りでない。
ニ 液体状の核原料物質を容器(容器がタンク又は金属製中型容器の場合に限る。)に収納し、専用積載としないで運搬する場合は、容器は、ロに掲げる基準のほか、外運搬規則第九条第二項第二号 に定める基準に適合すること。ただし、核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所において運搬する場合は、この限りでない。
ホ 運搬する核原料物質を収納した容器の表面における文部科学大臣の定める線量当量率は、二ミリシーベルト毎時を超えないようにし、かつ、容器の表面から一メートルの距離における文部科学大臣の定める線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないようにすること。ただし、核原料物質の使用施設の内部において運搬する場合は、この限りでない。
ヘ 運搬する核原料物質を収納した容器の表面の放射性物質の密度が第三号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。ただし、核原料物質の使用施設の内部において運搬する場合は、この限りでない。
ト 核原料物質を運搬する場合は、容器の表面の見やすい箇所に、次に掲げる事項を鮮明に表示しておくこと。ただし、核原料物質の使用施設の内部において運搬する場合は、この限りでない。
(1) 核原料物質の種類及び量
(2) 荷送人又は荷受人の氏名又は名称及び住所
十三 核原料物質の貯蔵は、次に定めるところにより行うこと。
イ 核原料物質の貯蔵は、核原料物質の貯蔵施設において行うこと。
ロ 核原料物質の貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
(記録)
第三条 法第五十七条の八第六項 の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
|
記録事項
|
記録すべき場合
|
保存期間
|
|
一 核原料物質の種類別の受渡量及び在庫量
|
毎月一回
|
十年間
|
|
二 放射線管理記録
イ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度
|
一日間の平均濃度にあつては毎日一回、三月間の平均濃度にあつては三月ごとに一回
|
十年間
|
|
ロ 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度
|
毎週一回
|
十年間
|
|
ハ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を、核原料物質使用者及び国際規制物資使用者等(国際規制物資である核原料物質(法第五十七条の八第一項第三号の核原料物質を除く。)を使用する国際規制物資使用者及び旧国際規制物資使用者等をいう。以下同じ。)に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により核原料物質使用者及び国際規制物資使用者等が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量
|
一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回
|
第五項に定める期間
|
|
ニ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量
|
原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。)
|
第五項に定める期間
|
|
ホ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴
|
その者が当該業務に就く時
|
第五項に定める期間
|
|
ヘ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法
|
廃棄のつど
|
使用の廃止までの期間
|
|
ト 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法
|
封入又は固型化のつど
|
使用の廃止までの期間
|
|
三 核原料物質の使用施設の事故記録
イ 事故の発生及び復旧の時
|
そのつど
|
使用の廃止までの期間
|
|
ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置
|
そのつど
|
使用の廃止までの期間
|
|
ハ 事故の原因
|
そのつど
|
使用の廃止までの期間
|
|
ニ 事故後の処置
|
そのつど
|
使用の廃止までの期間
|
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
3 第一項の表第二号ロの線量当量率並びに同号ハ及びニの線量は、それぞれ文部科学大臣の定めるところにより記録するものとする。
4 第一項の表第二号ハの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
5 第一項の表第二号ハからホまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において核原料物質使用者がその記録を文部科学大臣の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
6 核原料物質使用者は、第一項の表第二号ハの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れるときに交付しなければならない。
7 第五項の原子力規制委員会の指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。
(電磁的方法による保存)
第三条の二 法第五十七条の八第六項 に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(準用)
第三条の三 前二条の規定は、法第六十一条の七 の規定による国際規制物資使用者等の記録について準用する。
(使用の廃止の届出)
第三条の四 法第五十七条の八第七項 の規定により、核原料物質使用者が当該届出に係る核原料物質のすべての使用を廃止したときは、その廃止の日から三十日以内に次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃止に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 使用の届出の年月日
四 廃止の年月日
五 廃止の理由
2 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
(解散等の届出)
第四条 法第五十七条の八第八項 の規定により、核原料物質使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 解散又は死亡に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 核原料物質使用者が解散し又は死亡した年月日
四 解散の理由
2 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
(事故故障等の報告)
第五条 法第六十二条の三 の規定により、核原料物質使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
一 核原料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
二 核原料物質の使用施設の故障(核原料物質の使用に及ぼす支障が軽微なものを除く。)があつたとき。
三 核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物が異常に漏えいしたとき。
四 放射線業務従事者について第二条第五号イの線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
五 前各号のほか、核原料物質の使用施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
2 核原料物質使用者は、工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合であつて次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
一 放射性廃棄物により異常な汚染が生じたとき。
二 廃棄に従事する者について第二条第十一号の二ハの線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
三 前二号のほか、廃棄に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(報告の徴収)
第六条 核原料物質使用者は、毎年、工場又は事業所ごとに、六月三十日及び十二月三十一日における核原料物質の在庫量について、別記様式第一による報告書を作成し、それぞれ当該期日後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、当該在庫量に含まれるウランの量及びトリウムの量を合計した数量が五百グラム未満である場合は、この限りでない。
2 前項の報告書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
(準用)
第七条 前二条の規定は、国際規制物資使用者等について準用する。この場合において、第五条第一項及び前条第一項中「核原料物質」とあるのは「国際規制物資である核原料物質」と読み替えるものとする。
(届出書類の提出部数)
第八条 法第五十七条の八第一項 及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十五条 の規定に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
(身分を示す証明書)
第九条 法第六十八条第六項 の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第十条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第三のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一 第三条の四第一項の書類
二 第四条第一項の書類
(フレキシブルディスクの構造)
第十一条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第十二条 第十条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2 第十条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十三条 第十条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 提出者の氏名又は名称
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十三号)の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
1 この府令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この府令は、平成三年一月一日から施行する。
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
この府令は、平成十年四月二十日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条 この府令は公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号、以下「改正法」という。)の施行前に開始された改正法による改正前の法第六十八条第一項の規定による立入検査(保障措置協定に基づく保障措置の実施の確保のために行うものに限る。)は、この総理府令による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則第四条の二の三第一項の規定の適用については、保障措置検査とみなす。
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第五条、第七条及び第八条の改正規定(「20万円」を「30万円」に改める部分に限る。)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百五十七号)の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
1 この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に運搬されている核原料物質については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条本文の政令で定める日(平成十五年三月十七日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
1 この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。